平七の小槌(こづち)(2)
平七の小槌(こづち)(2)
2024/12/24(火) 08:30
(*神社やお寺に由来する伝承や日本に残る昔物語。今なら無料で全て読むことができます。メニューの『神社・お寺』から)
畑に到着し、日が落ちるまで、懸命に働いた。少しでも収穫を多くし、女房のミツを喜ばせ、生活を楽にしてやりたい、その一心だった。
畑仕事を終えると、小槌を発見した場所に戻した。
帰路につきながらも、ひょっとしたら、畑にまた火の玉が表れるかもしれない。何者かに荒らされるかもしれない、と後ろ髪を引かれる思いだった。
「いま帰った」
男は一日の疲れから声も絶え絶えに、戸を開けた。
傾いた自分の家の中から、どこかキラキラと黄金に輝くような雰囲気を感じた。
しかし、中からは返事がない。
とうとうミツは愛想をつかし、出ていったのだろうか?と男は不安になった。
土間に足を踏み入れ、もう一度、いま戻った、と伝えた。
「……。お帰りなさいませ」
透き通るような響きが奥から聞こえてきた。ミツのしわがれた声ではなかった。
「声が若いようだが、あんたは誰だい?」
「旦那様、お帰りなさいませ」
そう続ける声の方に目を向けたとき、男は腰を抜かしそうになった。
若くてきれいな女が三つ指をついて、頭を下げている。
「お、おまえは誰じゃ?」
そう訊ねると、女は顔をあげ不思議そうな目でこう答えた。
「なにをおっしゃるのです。おまえさま。ミツでございます」
「ば、馬鹿をいうな。わたしの女房はもっと年を食っておる。ミツをどこに隠した?」
心配になり、あたりを見回した。
もう一度女が口を開いた。
「旦那様、よく御覧くださいませ」
輝かしい肌の女がそう告げるので、男は女の顔をまじまじと見た。確かにどこかで見たことある顔だった。そしてそれが遠い記憶に追いやっていた若い頃のミツの表情であることがわかった。まぎれもない、目の前の女はミツのようである。
「お、おまえ、本当にミツなのか?」
「そうですよ、旦那様。わたしも不思議なのです。あなた様が、朝でかけられてからすぐに、不思議なことが起こりました。姿も顔かたちも、心持ちまで若がえっていくのでございます」
「ば、馬鹿な」
と言いながら、男は朝の道すがら、ミツが若い時に戻ればいい、と小槌を振りながら言ったことを思いだした。
「さては、あれは願いを叶える打出の小槌だったのか」
そう叫ぶと、男は茫然と立ち尽くした。とんでもない事態を引き起こしてしまった、と感じた。その瞬間、小槌を畑に置いてきたことを思い出した。急いで畑に戻らねばならない。あの夜、目の前に出現した火の玉が置き忘れた小槌は、どのような願いでもかなえられる素敵な贈り物だったのかもしれない。仮に打出の小槌であれば願い事が何でも叶うのだ。自分の真の願い事はこんなことではない、と焦った。
男が家を飛び出すと、すでに暗くなっていた。闇に沈む畑の前で男は小槌を探そうとした。見当たらない。
目の前に、あの日のように、きれいな青い炎がいくつも集まってきた。
反射的に腰が引けたが、小槌も必要だった。
ひとつ、絶対に言わねばならない願い事がそのとき男にはあったからだ。
火の玉の群れが小槌をすでに取り戻したのだろう。
畑の土に足を沈ませながら、必死に男は火の玉に近づいて行った。
熱で頬が焼けそうになった。
「火の玉様。どなたか存じませんが、小槌をもう一度だけわたしに使わせてください。ひとつだけどうしてもかなえていただきたい願い事がございます」
青い炎に向かい、必死で叫んだ。
あたりが張り詰めたように静かになった。炎だけがボッ、ボッと音を響かせ燃え上がる。宙に浮いているいくつかの炎に男は囲まれた。更に、中央では、小槌が浮いて揺らいでいるのがわかった。
――この小槌を渡せ、ということか?
重い声が男の耳に届いた。それは魂に響くようなずしりとした言葉であり、火の玉が自分に話しかけてきたのだと平七にも反射的に理解できた。
「はい、そうでございます」
――ひとつの願い事をすでにかなえてやったはずだが?
「申し訳ございません。まさか打出の小槌だとは知らずに、誤った願いを伝えてしまいました」
――小槌で願いをかなえられるのはひとつだけだ。
「そこを、なんとかお願いいたしやす」
土に埋もれながら、男は土下座した。
――いま我らで話し合う。
声がそういうと、しばらくあたりは静まり返った。
炎だけが、時折、大きくなったり小さくなったりしていた。
――仕方ない。今回は特別に一度だけ、願いをゆるす。
「あ、ありがとうございます」
礼を述べると、炎とともに、小槌が男の目の前にゆっくりと降りてきた。
――それを手に掴み、願い事を唱えるのだ。ただし、小槌はすでに燃え上がり熱くなっている。握った途端、おまえの手は焼けただれるだろう。
伸ばしかけた手を平七はぴくりと止めた。全身に汗が流れた。
「わたしの手は畑仕事で使い物にならなくなる、ということでございましょうか?」
ミツの顔が脳裏によぎった。仮に平七が野良仕事をできなくなったとしたら、ミツの生活はどうなるのだろうか?そう不安がよぎった。生涯幸せにする、と約束し、数十年前に一緒になったというのに、いまだ幸せにしてやれていない。そのうえ、稼ぎ頭である自分が、畑仕事に行けなくなる、という。
額から汗がとまらない。
一瞬迷ったが、それでも、ひとつの願いをあきらめきれなった。それほど男にとって重要なものだった。
平七は燃え盛る小槌にゆっくりと手を伸ばし、それを握った。熱い鉄の塊を手のひらに押し当てられたような衝撃が抜け、絶叫しそうになった。
しかし、我を忘れ、ひとつの願いを必死に叫んで小槌をふった。
つづく
(*メニュー欄『神社・お寺』から物語のつづきや他の昔物語を今なら全て無料で読むことができます。)
物語についてのご意見はこちらから
畑に到着し、日が落ちるまで、懸命に働いた。少しでも収穫を多くし、女房のミツを喜ばせ、生活を楽にしてやりたい、その一心だった。
畑仕事を終えると、小槌を発見した場所に戻した。
帰路につきながらも、ひょっとしたら、畑にまた火の玉が表れるかもしれない。何者かに荒らされるかもしれない、と後ろ髪を引かれる思いだった。
「いま帰った」
男は一日の疲れから声も絶え絶えに、戸を開けた。
傾いた自分の家の中から、どこかキラキラと黄金に輝くような雰囲気を感じた。
しかし、中からは返事がない。
とうとうミツは愛想をつかし、出ていったのだろうか?と男は不安になった。
土間に足を踏み入れ、もう一度、いま戻った、と伝えた。
「……。お帰りなさいませ」
透き通るような響きが奥から聞こえてきた。ミツのしわがれた声ではなかった。
「声が若いようだが、あんたは誰だい?」
「旦那様、お帰りなさいませ」
そう続ける声の方に目を向けたとき、男は腰を抜かしそうになった。
若くてきれいな女が三つ指をついて、頭を下げている。
「お、おまえは誰じゃ?」
そう訊ねると、女は顔をあげ不思議そうな目でこう答えた。
「なにをおっしゃるのです。おまえさま。ミツでございます」
「ば、馬鹿をいうな。わたしの女房はもっと年を食っておる。ミツをどこに隠した?」
心配になり、あたりを見回した。
もう一度女が口を開いた。
「旦那様、よく御覧くださいませ」
輝かしい肌の女がそう告げるので、男は女の顔をまじまじと見た。確かにどこかで見たことある顔だった。そしてそれが遠い記憶に追いやっていた若い頃のミツの表情であることがわかった。まぎれもない、目の前の女はミツのようである。
「お、おまえ、本当にミツなのか?」
「そうですよ、旦那様。わたしも不思議なのです。あなた様が、朝でかけられてからすぐに、不思議なことが起こりました。姿も顔かたちも、心持ちまで若がえっていくのでございます」
「ば、馬鹿な」
と言いながら、男は朝の道すがら、ミツが若い時に戻ればいい、と小槌を振りながら言ったことを思いだした。
「さては、あれは願いを叶える打出の小槌だったのか」
そう叫ぶと、男は茫然と立ち尽くした。とんでもない事態を引き起こしてしまった、と感じた。その瞬間、小槌を畑に置いてきたことを思い出した。急いで畑に戻らねばならない。あの夜、目の前に出現した火の玉が置き忘れた小槌は、どのような願いでもかなえられる素敵な贈り物だったのかもしれない。仮に打出の小槌であれば願い事が何でも叶うのだ。自分の真の願い事はこんなことではない、と焦った。
男が家を飛び出すと、すでに暗くなっていた。闇に沈む畑の前で男は小槌を探そうとした。見当たらない。
目の前に、あの日のように、きれいな青い炎がいくつも集まってきた。
反射的に腰が引けたが、小槌も必要だった。
ひとつ、絶対に言わねばならない願い事がそのとき男にはあったからだ。
火の玉の群れが小槌をすでに取り戻したのだろう。
畑の土に足を沈ませながら、必死に男は火の玉に近づいて行った。
熱で頬が焼けそうになった。
「火の玉様。どなたか存じませんが、小槌をもう一度だけわたしに使わせてください。ひとつだけどうしてもかなえていただきたい願い事がございます」
青い炎に向かい、必死で叫んだ。
あたりが張り詰めたように静かになった。炎だけがボッ、ボッと音を響かせ燃え上がる。宙に浮いているいくつかの炎に男は囲まれた。更に、中央では、小槌が浮いて揺らいでいるのがわかった。
――この小槌を渡せ、ということか?
重い声が男の耳に届いた。それは魂に響くようなずしりとした言葉であり、火の玉が自分に話しかけてきたのだと平七にも反射的に理解できた。
「はい、そうでございます」
――ひとつの願い事をすでにかなえてやったはずだが?
「申し訳ございません。まさか打出の小槌だとは知らずに、誤った願いを伝えてしまいました」
――小槌で願いをかなえられるのはひとつだけだ。
「そこを、なんとかお願いいたしやす」
土に埋もれながら、男は土下座した。
――いま我らで話し合う。
声がそういうと、しばらくあたりは静まり返った。
炎だけが、時折、大きくなったり小さくなったりしていた。
――仕方ない。今回は特別に一度だけ、願いをゆるす。
「あ、ありがとうございます」
礼を述べると、炎とともに、小槌が男の目の前にゆっくりと降りてきた。
――それを手に掴み、願い事を唱えるのだ。ただし、小槌はすでに燃え上がり熱くなっている。握った途端、おまえの手は焼けただれるだろう。
伸ばしかけた手を平七はぴくりと止めた。全身に汗が流れた。
「わたしの手は畑仕事で使い物にならなくなる、ということでございましょうか?」
ミツの顔が脳裏によぎった。仮に平七が野良仕事をできなくなったとしたら、ミツの生活はどうなるのだろうか?そう不安がよぎった。生涯幸せにする、と約束し、数十年前に一緒になったというのに、いまだ幸せにしてやれていない。そのうえ、稼ぎ頭である自分が、畑仕事に行けなくなる、という。
額から汗がとまらない。
一瞬迷ったが、それでも、ひとつの願いをあきらめきれなった。それほど男にとって重要なものだった。
平七は燃え盛る小槌にゆっくりと手を伸ばし、それを握った。熱い鉄の塊を手のひらに押し当てられたような衝撃が抜け、絶叫しそうになった。
しかし、我を忘れ、ひとつの願いを必死に叫んで小槌をふった。
つづく
(*メニュー欄『神社・お寺』から物語のつづきや他の昔物語を今なら全て無料で読むことができます。)
物語についてのご意見はこちらから
(*神社やお寺に由来する伝承や日本に残る昔物語。今なら無料で全て読むことができます。メニューの『神社・お寺』から)
畑に到着し、日が落ちるまで、懸命に働いた。少しでも収穫を多くし、女房のミツを喜ばせ、生活を楽にしてやりたい、その一心だった。
畑仕事を終えると、小槌を発見した場所に戻した。
帰路につきながらも、ひょっとしたら、畑にまた火の玉が表れるかもしれない。何者かに荒らされるかもしれない、と後ろ髪を引かれる思いだった。
「いま帰った」
男は一日の疲れから声も絶え絶えに、戸を開けた。
傾いた自分の家の中から、どこかキラキラと黄金に輝くような雰囲気を感じた。
しかし、中からは返事がない。
とうとうミツは愛想をつかし、出ていったのだろうか?と男は不安になった。
土間に足を踏み入れ、もう一度、いま戻った、と伝えた。
「……。お帰りなさいませ」
透き通るような響きが奥から聞こえてきた。ミツのしわがれた声ではなかった。
「声が若いようだが、あんたは誰だい?」
「旦那様、お帰りなさいませ」
そう続ける声の方に目を向けたとき、男は腰を抜かしそうになった。
若くてきれいな女が三つ指をついて、頭を下げている。
「お、おまえは誰じゃ?」
そう訊ねると、女は顔をあげ不思議そうな目でこう答えた。
「なにをおっしゃるのです。おまえさま。ミツでございます」
「ば、馬鹿をいうな。わたしの女房はもっと年を食っておる。ミツをどこに隠した?」
心配になり、あたりを見回した。
畑に到着し、日が落ちるまで、懸命に働いた。少しでも収穫を多くし、女房のミツを喜ばせ、生活を楽にしてやりたい、その一心だった。
畑仕事を終えると、小槌を発見した場所に戻した。
帰路につきながらも、ひょっとしたら、畑にまた火の玉が表れるかもしれない。何者かに荒らされるかもしれない、と後ろ髪を引かれる思いだった。
「いま帰った」
男は一日の疲れから声も絶え絶えに、戸を開けた。
傾いた自分の家の中から、どこかキラキラと黄金に輝くような雰囲気を感じた。
しかし、中からは返事がない。
とうとうミツは愛想をつかし、出ていったのだろうか?と男は不安になった。
土間に足を踏み入れ、もう一度、いま戻った、と伝えた。
「……。お帰りなさいませ」
透き通るような響きが奥から聞こえてきた。ミツのしわがれた声ではなかった。
「声が若いようだが、あんたは誰だい?」
「旦那様、お帰りなさいませ」
そう続ける声の方に目を向けたとき、男は腰を抜かしそうになった。
若くてきれいな女が三つ指をついて、頭を下げている。
「お、おまえは誰じゃ?」
そう訊ねると、女は顔をあげ不思議そうな目でこう答えた。
「なにをおっしゃるのです。おまえさま。ミツでございます」
「ば、馬鹿をいうな。わたしの女房はもっと年を食っておる。ミツをどこに隠した?」
心配になり、あたりを見回した。
https://mnk-news.net/images/logo.png
名字・名前・家系図/家紋ニュース
《F(エフ)》


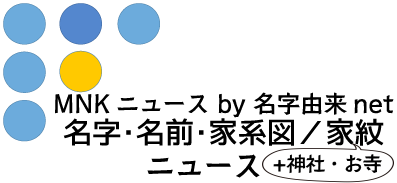













































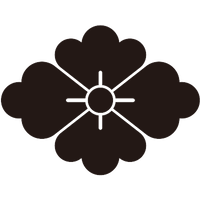 花菱
花菱


