弥助の赤い袋とお稲荷さま(1)
弥助の赤い袋とお稲荷さま(1)(*神社やお寺に由来する伝承や日本に残る昔物語。今なら無料で全て読むことができます。メニューの『神社・お寺』から)
昔、下総の国に「いちかわ」という村があった。太日川(おおいがわ)が流れ、川の近くで市が開かれにぎわう日もあり、それがいちかわ村の名の由来となった。太日川は時に暴れた。暴雨になると、土で固めた堤を乗り越え、大水が村を飲み込む。奈良の昔から人が住んでいるにもかかわらず、おかげで一帯は貧しかった。海も目の前まで迫っている土地だけに沼地も多い。
近くに小さな稲荷神社がある。社といえるほどのものもなく、石の祠を積み上げ、芦に埋もれている場所だ。
ここに毎日足を向けている子供がいた。名は弥助(やすけ)と言い、年のころは六つだった。住む家から、半里(二キロ)の道のりだった。
「おっかあの命が、今日も生きながらえることができました。ありがとうごぜえやす」
そうつぶやくと、自分の昼を我慢して握った小さなまるい飯つぶを祠にそなえた。小さく背を丸め、膝をついた。懐から小ぶりの布袋も石段に供えた。
弥助の家は貧しかった。あたりは、ぬかるんでいて、作物ができない。多くの大人たちは、一里ほど先にある弘法寺参詣者に向け、参道で、団子や、竹を削った箸などを売って生業をたてていた。
父を早くに病でなくし、唯一の働き手である弥助の母親が、数年前から床に臥せる日が多くなった。はやり病だと判断した医者は、隣の作兵衛の息子の見立てを誤ったことがある。信用おけなかったが、案の定、弥助のおかあも咳き込むことが日増しに多くなり、落ちくぼんだ目に変貌した。
「これをお稲荷さまに」
朝、弥助が目覚めると、隣の布団で寝ている母親の目が少し微笑んで、赤色のまるまった布を弥助の胸上に置いた。
――お稲荷さまが、おかあを今日も生かしてくれているのだ。
おかあの手のぬくもりがたったいまも感じられることがうれしくて、弥助は、母の手の平ごと、その袋を握った。糸で封がされている。中に何が入っているのか弥助は知らなかった。
つづく
(*メニュー欄『神社・お寺』から物語のつづきや他の昔物語を今なら全て無料で読むことができます。)
物語についてのご意見はこちらから
(*神社やお寺に由来する伝承や日本に残る昔物語。今なら無料で全て読むことができます。メニューの『神社・お寺』から)
昔、下総の国に「いちかわ」という村があった。太日川(おおいがわ)が流れ、川の近くで市が開かれにぎわう日もあり、それがいちかわ村の名の由来となった。太日川は時に暴れた。暴雨になると、土で固めた堤を乗り越え、大水が村を飲み込む。奈良の昔から人が住んでいるにもかかわらず、おかげで一帯は貧しかった。海も目の前まで迫っている土地だけに沼地も多い。
近くに小さな稲荷神社がある。社といえるほどのものもなく、石の祠を積み上げ、芦に埋もれている場所だ。
ここに毎日足を向けている子供がいた。名は弥助(やすけ)と言い、年のころは六つだった。住む家から、半里(二キロ)の道のりだった。
「おっかあの命が、今日も生きながらえることができました。ありがとうごぜえやす」
そうつぶやくと、自分の昼を我慢して握った小さなまるい飯つぶを祠にそなえた。小さく背を丸め、膝をついた。懐から小ぶりの布袋も石段に供えた。
弥助の家は貧しかった。あたりは、ぬかるんでいて、作物ができない。多くの大人たちは、一里ほど先にある弘法寺参詣者に向け、参道で、団子や、竹を削った箸などを売って生業をたてていた。


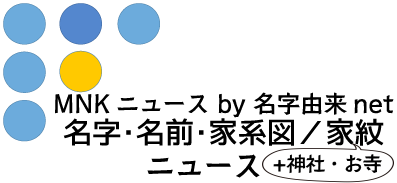






































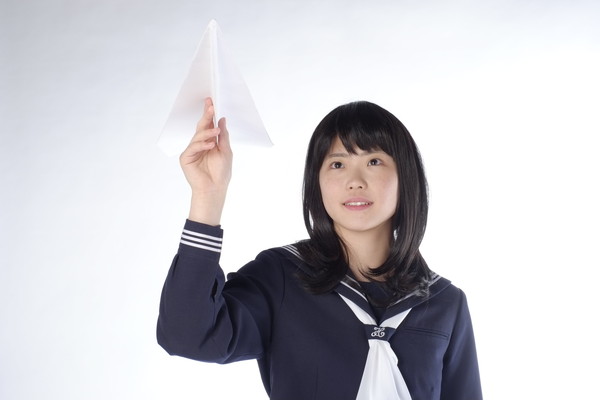








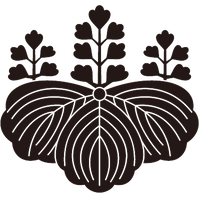 五七桐
五七桐



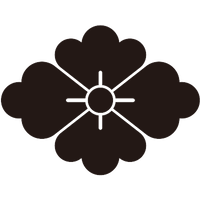 花菱
花菱
