名字ランキング 第9位 小林
名字ランキング 第9位 小林
2021/01/01(金) 08:30
名字博士と愛ちゃんが 小林姓について話しています。
「大林さんや林さんより小林さんが多いのはなぜ?」
「大林さんは約二万三、五〇〇人、林さんは約五七万人。両方あわせても小林さんにはかなわない。どうして小林さんが多いかというと、小林という地名の場所が住みやすいからさ」
「そうなの?」
「大林や林のように林が深いと稲を荒らす鹿や猪が棲んでいるかも知れない。林が山につながっていると熊がやって来ることだってある。こわくておちおち住んじゃいられない」
「だったら林のないところに住めばいいじゃない」
「そうすると煮炊きや風呂に使う薪(たきぎ)に不自由するだろう。それに雑木林は田畑を風害から守ってくれる。家の裏に小さな林、前に小川が流れていれば、田畑や生活に必要な水にも困らない。まさに安心して暮らせる場所というわけさ」
「それで小林さんが増えたのね」
「理由はほかにもある。そもそも小林とはオハヤシという言葉が変化したものでもある」
「オハヤシ?」
「神楽(かぐら)や歌舞伎、能で音曲を担当する人々を囃子方(はやしかた)というんだ。彼らは笛・小鼓(こつづみ)・大鼓・太鼓(たいこ)で舞台を盛り上げるのだが、囃子(はやし)とは声や楽器で神様をほめたたえることをいい、生き物を〈生(は)やす〉にも通じる大変におめでたい言葉なんだ。このハヤシが小林のハヤシには秘められているのだよ」
「そうなる。ただの小さな林だと思っちゃいけないのね」
「その通り。小林の小だって御のことだといわれている。実は小林とは御林のことなんだ。御林とは神聖な林のこと。森や林を切り開いて土地を開拓するとき、土地の神様の住処(すみか)として少しだけ林を残した。これが鎮守の森といわれるもので、そこには神社が建てられた。小林さんには神主が多いが、それは小林という地名が神様の森に由来していることが多いからだ。また小林さんは御囃子(おはやし)で神様を喜ばせることも上手だったからね。神主は天職だったんだよ」
「なら御林と名乗ればよかったのに」
「そこが日本人のおくゆかしいところだよ。神様につけられる御を地名や名字に使うことは恐れ多いとして避(さ)けたのさ。御田は三田、御浦は三浦と変えて、やはり御を遠慮して三を使っている。まあ御神本(みかもと)のように御を使っているものも多少はあるが、数は少ない」
「小林さんはどの地方に多いの?」
「日本で一番小林さんが多いのは長野県だ。次いで新潟県に多く、群馬県などの関東にも大勢いる。長野県の小林さんといえば俳人の小林一茶がいるね。〈やせ蛙(かえる)まけるな一茶これにあり〉。ケンカをしているやせたカエルに向かって、負けるな、自分がついているぞ! と励ましている句だ。一茶は弱者にエールを送る句をたくさん詠んだ。だからその句はいつまでも愛されているわけだ。そして長野・群馬県に小林さんが多いのは小林さんが率いた武士団が大いに活躍したからだろう。小林さんにゆかりのある者やあやかりたい者が小林という名字を名乗って、どんどん増えたわけだ」
「大林さんや林さんより小林さんが多いのはなぜ?」
「大林さんは約二万三、五〇〇人、林さんは約五七万人。両方あわせても小林さんにはかなわない。どうして小林さんが多いかというと、小林という地名の場所が住みやすいからさ」
「そうなの?」
「大林や林のように林が深いと稲を荒らす鹿や猪が棲んでいるかも知れない。林が山につながっていると熊がやって来ることだってある。こわくておちおち住んじゃいられない」
「だったら林のないところに住めばいいじゃない」
「そうすると煮炊きや風呂に使う薪(たきぎ)に不自由するだろう。それに雑木林は田畑を風害から守ってくれる。家の裏に小さな林、前に小川が流れていれば、田畑や生活に必要な水にも困らない。まさに安心して暮らせる場所というわけさ」
「それで小林さんが増えたのね」
「理由はほかにもある。そもそも小林とはオハヤシという言葉が変化したものでもある」
「オハヤシ?」
「神楽(かぐら)や歌舞伎、能で音曲を担当する人々を囃子方(はやしかた)というんだ。彼らは笛・小鼓(こつづみ)・大鼓・太鼓(たいこ)で舞台を盛り上げるのだが、囃子(はやし)とは声や楽器で神様をほめたたえることをいい、生き物を〈生(は)やす〉にも通じる大変におめでたい言葉なんだ。このハヤシが小林のハヤシには秘められているのだよ」
「そうなる。ただの小さな林だと思っちゃいけないのね」
「その通り。小林の小だって御のことだといわれている。実は小林とは御林のことなんだ。御林とは神聖な林のこと。森や林を切り開いて土地を開拓するとき、土地の神様の住処(すみか)として少しだけ林を残した。これが鎮守の森といわれるもので、そこには神社が建てられた。小林さんには神主が多いが、それは小林という地名が神様の森に由来していることが多いからだ。また小林さんは御囃子(おはやし)で神様を喜ばせることも上手だったからね。神主は天職だったんだよ」
「なら御林と名乗ればよかったのに」
「そこが日本人のおくゆかしいところだよ。神様につけられる御を地名や名字に使うことは恐れ多いとして避(さ)けたのさ。御田は三田、御浦は三浦と変えて、やはり御を遠慮して三を使っている。まあ御神本(みかもと)のように御を使っているものも多少はあるが、数は少ない」
「小林さんはどの地方に多いの?」
「日本で一番小林さんが多いのは長野県だ。次いで新潟県に多く、群馬県などの関東にも大勢いる。長野県の小林さんといえば俳人の小林一茶がいるね。〈やせ蛙(かえる)まけるな一茶これにあり〉。ケンカをしているやせたカエルに向かって、負けるな、自分がついているぞ! と励ましている句だ。一茶は弱者にエールを送る句をたくさん詠んだ。だからその句はいつまでも愛されているわけだ。そして長野・群馬県に小林さんが多いのは小林さんが率いた武士団が大いに活躍したからだろう。小林さんにゆかりのある者やあやかりたい者が小林という名字を名乗って、どんどん増えたわけだ」
名字博士と愛ちゃんが 小林姓について話しています。
「大林さんや林さんより小林さんが多いのはなぜ?」
「大林さんは約二万三、五〇〇人、林さんは約五七万人。両方あわせても小林さんにはかなわない。どうして小林さんが多いかというと、小林という地名の場所が住みやすいからさ」
「そうなの?」
「大林や林のように林が深いと稲を荒らす鹿や猪が棲んでいるかも知れない。林が山につながっていると熊がやって来ることだってある。こわくておちおち住んじゃいられない」
「だったら林のないところに住めばいいじゃない」
「そうすると煮炊きや風呂に使う薪(たきぎ)に不自由するだろう。それに雑木林は田畑を風害から守ってくれる。家の裏に小さな林、前に小川が流れていれば、田畑や生活に必要な水にも困らない。まさに安心して暮らせる場所というわけさ」
「それで小林さんが増えたのね」
「理由はほかにもある。そもそも小林とはオハヤシという言葉が変化したものでもある」
「オハヤシ?」
「神楽(かぐら)や歌舞伎、能で音曲を担当する人々を囃子方(はやしかた)というんだ。彼らは笛・小鼓(こつづみ)・大鼓・太鼓(たいこ)で舞台を盛り上げるのだが、囃子(はやし)とは声や楽器で神様をほめたたえることをいい、生き物を〈生(は)やす〉にも通じる大変におめでたい言葉なんだ。このハヤシが小林のハヤシには秘められているのだよ」
「そうなる。ただの小さな林だと思っちゃいけないのね」
「その通り。小林の小だって御のことだといわれている。実は小林とは御林のことなんだ。御林とは神聖な林のこと。森や林を切り開いて土地を開拓するとき、土地の神様の住処(すみか)として少しだけ林を残した。これが鎮守の森といわれるもので、そこには神社が建てられた。小林さんには神主が多いが、それは小林という地名が神様の森に由来していることが多いからだ。また小林さんは御囃子(おはやし)で神様を喜ばせることも上手だったからね。神主は天職だったんだよ」
「なら御林と名乗ればよかったのに」
「そこが日本人のおくゆかしいところだよ。神様につけられる御を地名や名字に使うことは恐れ多いとして避(さ)けたのさ。御田は三田、御浦は三浦と変えて、やはり御を遠慮して三を使っている。まあ御神本(みかもと)のように御を使っているものも多少はあるが、数は少ない」
「小林さんはどの地方に多いの?」
「日本で一番小林さんが多いのは長野県だ。次いで新潟県に多く、群馬県などの関東にも大勢いる。長野県の小林さんといえば俳人の小林一茶がいるね。〈やせ蛙(かえる)まけるな一茶これにあり〉。ケンカをしているやせたカエルに向かって、負けるな、自分がついているぞ! と励ましている句だ。一茶は弱者にエールを送る句をたくさん詠んだ。だからその句はいつまでも愛されているわけだ。そして長野・群馬県に小林さんが多いのは小林さんが率いた武士団が大いに活躍したからだろう。小林さんにゆかりのある者やあやかりたい者が小林という名字を名乗って、どんどん増えたわけだ」
「大林さんや林さんより小林さんが多いのはなぜ?」
「大林さんは約二万三、五〇〇人、林さんは約五七万人。両方あわせても小林さんにはかなわない。どうして小林さんが多いかというと、小林という地名の場所が住みやすいからさ」
「そうなの?」
「大林や林のように林が深いと稲を荒らす鹿や猪が棲んでいるかも知れない。林が山につながっていると熊がやって来ることだってある。こわくておちおち住んじゃいられない」
「だったら林のないところに住めばいいじゃない」
「そうすると煮炊きや風呂に使う薪(たきぎ)に不自由するだろう。それに雑木林は田畑を風害から守ってくれる。家の裏に小さな林、前に小川が流れていれば、田畑や生活に必要な水にも困らない。まさに安心して暮らせる場所というわけさ」
「それで小林さんが増えたのね」
「理由はほかにもある。そもそも小林とはオハヤシという言葉が変化したものでもある」
「オハヤシ?」
「神楽(かぐら)や歌舞伎、能で音曲を担当する人々を囃子方(はやしかた)というんだ。彼らは笛・小鼓(こつづみ)・大鼓・太鼓(たいこ)で舞台を盛り上げるのだが、囃子(はやし)とは声や楽器で神様をほめたたえることをいい、生き物を〈生(は)やす〉にも通じる大変におめでたい言葉なんだ。このハヤシが小林のハヤシには秘められているのだよ」
「そうなる。ただの小さな林だと思っちゃいけないのね」
「その通り。小林の小だって御のことだといわれている。実は小林とは御林のことなんだ。御林とは神聖な林のこと。森や林を切り開いて土地を開拓するとき、土地の神様の住処(すみか)として少しだけ林を残した。これが鎮守の森といわれるもので、そこには神社が建てられた。小林さんには神主が多いが、それは小林という地名が神様の森に由来していることが多いからだ。また小林さんは御囃子(おはやし)で神様を喜ばせることも上手だったからね。神主は天職だったんだよ」
「なら御林と名乗ればよかったのに」
「そこが日本人のおくゆかしいところだよ。神様につけられる御を地名や名字に使うことは恐れ多いとして避(さ)けたのさ。御田は三田、御浦は三浦と変えて、やはり御を遠慮して三を使っている。まあ御神本(みかもと)のように御を使っているものも多少はあるが、数は少ない」
「小林さんはどの地方に多いの?」
「日本で一番小林さんが多いのは長野県だ。次いで新潟県に多く、群馬県などの関東にも大勢いる。長野県の小林さんといえば俳人の小林一茶がいるね。〈やせ蛙(かえる)まけるな一茶これにあり〉。ケンカをしているやせたカエルに向かって、負けるな、自分がついているぞ! と励ましている句だ。一茶は弱者にエールを送る句をたくさん詠んだ。だからその句はいつまでも愛されているわけだ。そして長野・群馬県に小林さんが多いのは小林さんが率いた武士団が大いに活躍したからだろう。小林さんにゆかりのある者やあやかりたい者が小林という名字を名乗って、どんどん増えたわけだ」
https://mnk-news.net/images/logo.png
名字・名前・家系図/家紋ニュース
《MAX10》


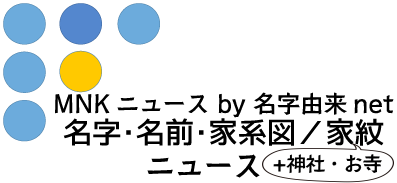



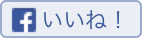























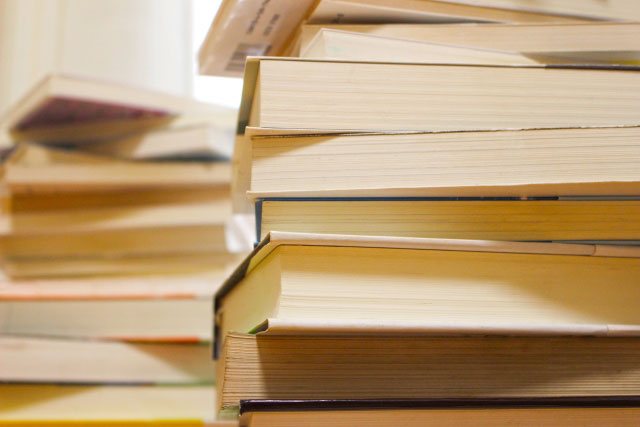













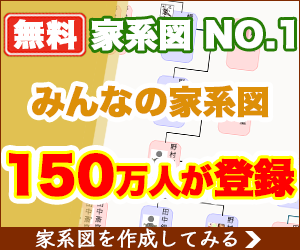


 丸に割三引両
丸に割三引両
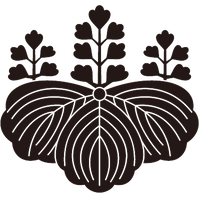 五七桐
五七桐

